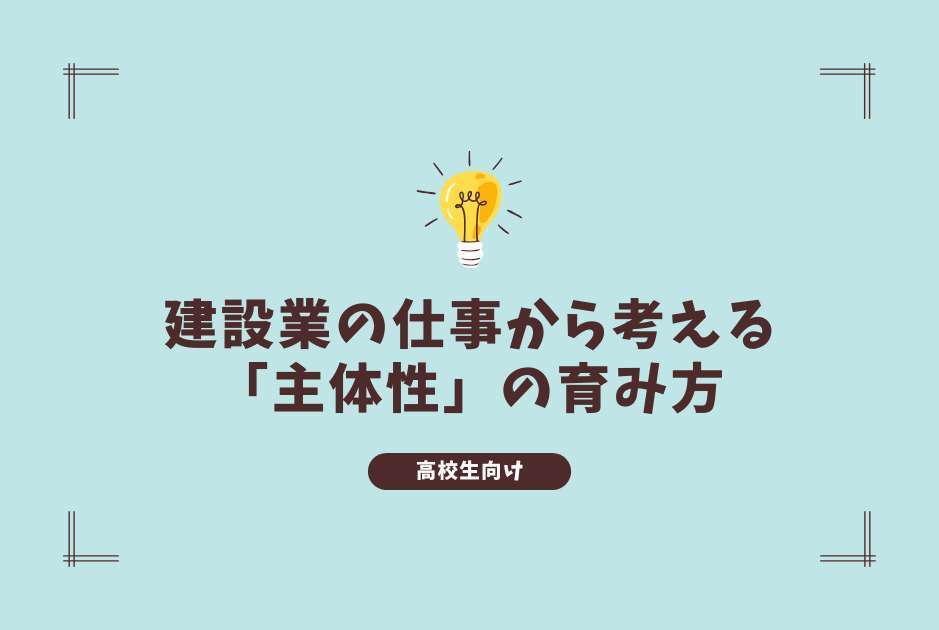2024年、株式会社リクルートが発表した調査によると、
高校生が「将来に必要な力」だと感じているものの第1位は「主体性」(51.5%)でした。
つまり、自分で考え、行動する力が、これからの時代に欠かせないと多くの高校生が実感しているのです。
その背景には、「正解のない時代」と言われるような社会の変化や、
アクティブラーニングや探究活動といった教育現場の新しい学び方の広がり、
そして、進路選択を間近に控えるなかでの将来への漠然とした不安などがあるのではないでしょうか。
今の学校では、ただ先生の話を聞いて覚えるだけではなく、
自分で調べ、考え、言葉にし、行動することが大切だとされるようになってきました。
「自分で考えることが大事だよ」と先生に言われた経験のある人も少なくないと思います。
そこで今回の記事では、そんな高校生の皆さんに向けて、
「なぜ社会人には主体性が必要なのか」という基本的なところから、
建設業の仕事を通じて、主体性がどう育まれていくのかまで、わかりやすく紹介していきます。
▼ 目次
------------------------------------------------------------------
- そもそも「主体性」とは?
- もし「主体性」がなかったら? 社会で起きるリアルな困りごと
- 主体性は才能ではなく、後天的に身につくもの
- 建設業の仕事から考える、主体性の高め方
------------------------------------------------------------------
■ そもそも主体性とは?
まずはじめに、「主体性」という言葉の理解を深めていきたいと思います。
簡単に言えば、「誰かに言われて動くのではなく、自分で『こうしたい』『こうすべきだ』と考えて動けること」です。
例えば、こんな場面を想像してみてください。
お風呂の浴槽にお湯をためている途中で、偶然にも「もう少しで溢れそう!」という状況に気づいたとします。
そのとき、あなたは次のどちらの行動をとるでしょうか?
①「まあ、誰かが止めるでしょ」とそのまま立ち去る
②「このままだと水浸しになる!」と自分で判断して、すぐにお湯を止める
客観的に見て、主体性がある行動はどちらでしょうか?
さて、別の例も考えてみましょう。
文化祭の準備が始まったけれど、みんなスマホをいじったり雑談したりしていて、何をするか決まらないまま時間が過ぎていきます。
そのとき、あなたは次のどちらの行動をとるでしょうか?
①「まあ、そのうち誰かが言い出すでしょ」と何もしないまま様子を見る
②「このままじゃ間に合わない!」と自分から「まず○○から始めよう」と声をかけて動き出す
このように、「誰かの指示を待たずに、自分で気づいて動けるか」というのが、主体性の大きなポイントです。
ちょっとした日常の判断にも、主体性のある・なしはあらわれます。
■ もし主体性がなかったら?社会で困るリアルな困りごと
では次に、実際の社会における「主体性」について考えていきましょう。
家庭や学校といった比較的守られた環境では、主体性が欠けていても周囲の大人や先生がフォローしてくれるため、大きな問題には発展しにくいものです。しかし、「仕事」となると話は別です。主体性の有無は、会社の生産性や安全性、さらには信頼性にも大きな影響を及ぼします。
例えば、以下のような場面を想像してみてください。
◆ 指示待ちで作業が滞る
職場で「言われたことしかやらない」「自分から動かない」人ばかりだと、誰かが指示を出すまで業務が進まず、納期に間に合わなくなるリスクが高まります。チーム全体のスピードも落ち、結果として生産性が低下してしまいます。
◆ 危険を見過ごしてしまう
とくに建設業や製造業など、現場での安全が最優先される職種では、「気づいたことを報告しない」「判断を他人に任せる」といった主体性の欠如が、大きな事故につながる恐れがあります。「たぶん大丈夫だろう」と流すことで、取り返しのつかない事態を招くことも。
◆ 信頼を失う
顧客や取引先とのやり取りの中で、相手からの質問に「わかりません」「担当に聞いてみます」と毎回答えるだけでは、信頼は築けません。主体性を持って「調べてみます」「自分で確認してみます」といった前向きな姿勢を見せることが、社会人としての評価にも直結します。
このように、主体性が欠けていることによって生じる“リアルな困りごと”は、職場のあちこちに存在しています。そしてそれは、周囲の負担を増やし、組織全体のパフォーマンスを落とす原因にもなります。
上記は組織全体にフォーカスした内容ですが、自分自身(個人)にもじわじわと悪影響を与えます。
1. モチベーションが下がる
「言われたことだけをやる」「自分の考えが反映されない」——
そんな日々が続くと、仕事への興味ややりがいはどんどん薄れていきます。
主体性がある人は、「自分で考えて動く→結果が出る→やりがいを感じる」という好循環が生まれやすいのですが、受け身の姿勢だとその逆。「やらされ感」が強まり、仕事がただの“作業”に変わってしまいます。
2. 成長の機会を逃す
社会に出てから成長していくには、「自分から動く力」が不可欠です。
主体的に行動する人は、新しい業務にチャレンジしたり、先輩の仕事を見て学んだりする中で、自然とスキルが磨かれていきます。
一方、指示を待つばかりの人には、そうした経験のチャンスがなかなか巡ってきません。結果として、周りと差が開きやすくなり、いつの間にか「できることが少ないまま」年次だけ重ねる、という状況に陥ってしまいます。
3. 人事評価にあらわれる
会社は、ただ「言われたことをこなす人」よりも、自ら考え行動できる人を高く評価する傾向にあります。
たとえ失敗しても、自分で動いた経験には価値があり、それが評価や昇給・昇格に反映されるケースは少なくありません。
逆に、常に受け身でいる人は「この人に任せて大丈夫か?」「成長意欲があるのか?」という懸念を持たれやすく、評価のチャンスを逃しがちです。
それは、将来のキャリアにも大きく影響します。
■ 建設業の仕事から考える、主体性の高め方
◆ 主体性が自然と育まれやすい建設業の仕事
建設業の現場には、主体性が自然と求められ、育つ条件が揃っています。
以下のような特徴が、日々の仕事の中で“考えて動く力”を引き出してくれるのです。
1. 状況が常に変化する(不確実性)
建設現場は一つとして同じ条件がありません。地形、天候、周囲の交通状況、使用する資材や重機の種類まで、その日その場で違いがあります。
たとえば、前日の雨で足場がぬかるんでいた場合、同じ作業手順は使えません。
「どうすれば安全に進められるか」「別ルートで搬入すべきか」といった判断が、即座に求められます。これが自然と、現場ごとの“考える力”を鍛えてくれるのです。
2. ゴールは共有されているが、進め方は任されている(裁量)
「配管を引く」「基礎を打つ」といった作業の目的(ゴール)は明確でも、そのやり方や順序、道具の選び方などは、ある程度作業者に任される部分があります。
たとえば、狭い場所での配管作業なら、手順を工夫しないと手が入らない。図面を見ながら「この順番でやればムダがないかも」と判断し、実行する必要があります。
こうした「自分なりの工夫と選択」が、仕事の中に日常的に組み込まれています。
3. チームの中で「自分の役割」を見つける(協働と自律)
建設現場は常に複数人で動くチームプレー。誰かが先行作業をしているとき、他の人は何をするかを考え、その場で“空いている仕事”を自分から見つけて動く必要があります。
たとえば、「今は親方が溶接中だから、自分は先に材料の整理をしておこう」といったように、指示がなくても現場全体を見て動けるかどうかが問われます。
自分の動きが全体に影響するという意識が、主体性の根っこになります。
主体性は「才能」ではなく「経験で育つもの」
ここまで紹介してきたように、建設業の仕事には「不確実性」「裁量」「協働と自律」といった要素がそろっています。これらはまさに、主体性を育てるために必要な“土壌”です。
でもこれは、何も建設業に限った話ではありません。
この3つの要素は、職種を問わず、そして日常生活の中でも経験できるものなのです。
◆ 不確実性 —— 予定通りにいかないことが当たり前
天候や現場条件の変化のように、日常でも「予想外」はたくさんあります。たとえば、急な予定変更や家庭のトラブル、想定外の問題に直面したとき——その状況にどう対応するかを自分で考えることは、まさに主体性のトレーニングです。
◆ 裁量 —— どうやるかは自分次第
会社でも学校でも、与えられた課題を“どうやるか”は人それぞれ。たとえば資料のまとめ方、店内の動線づくり、スケジュール管理の方法など、やり方に自由度がある場面では、自分で判断する力=主体性が自然と鍛えられます。
◆ 協働と自律 —— チームの中で「自分の動き」を決める
どんな環境でも、人と一緒に動く場面は必ずあります。職場のチーム、学校のグループ活動、家庭や地域の中でも、「自分が何をすべきか」「今、誰のために動くべきか」を考えることは、小さな“主体的行動”の連続です。
主体性は後天的に、じっくり育てられる
大事なのは、主体性はもともと持っているかどうかではなく、「経験を通じて身につけるもの」だということ。
建設業は、偶然にもその育成環境がそろっているからこそ、主体性が育ちやすい職種だと言えるのです。でも、同じような要素は他のどんな業界にも、そして日々の生活の中にもあります。
「考えて動く」「周りを見て判断する」「工夫する」という一つひとつの積み重ねが、あなたの中の“主体性”を、確実に育てていきます。
■ 最後に:建設業を知らなかった人へ、ぜひ選択肢として
主体性を育てる環境は、実はとても身近なところにあります。
建設業は、「体力勝負」や「職人の世界」といったイメージだけで語られがちですが、実際には自分で考え、動き、成長できる舞台が広がっている業界です。
もし今まで、建設業を就職の選択肢に入れていなかったとしたら、
この機会にぜひ、視野に入れてみてください。
あなたの中にある「考える力」や「工夫する力」は、きっと現場で輝きます。
私たちの会社でも、新しい仲間を募集しています。
経験の有無は問いません。少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ気軽にご応募ください。